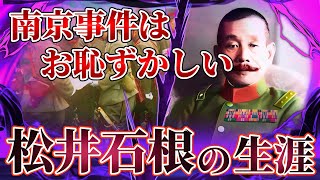英国議会の報告書の記載が記事になりました。記事にした産経新聞に感謝です。
ハマスによるイスラエル奇襲「南京大虐殺以来の蛮行」と英議会報告書 問われる対外発信https://t.co/SiQsitkK1b
「1200人近い罪のない人々が実際にハマスとその協力者によって殺害され、その多くは1937年の南京大虐殺以来、世界史上見られなかった残忍な蛮行の現場で殺された」と説明している。
— 産経ニュース (@Sankei_news) March 31, 2025
2023年10月7日のイスラム原理主義組織ハマスによるイスラエル奇襲について、英議会の報告書が「南京大虐殺以来の蛮行」と記述していることが分かった。虐殺の例えに南京事件を持ち出されたことで、日本政府の対外発信の在り方が問われそうだ。
報告書は、著名な歴史家で上院(貴族院)議員のアンドリュー・ロバーツ氏が責任者となって、英議会の超党派委員会が18日に公表。法医学的証拠や生存者の証言などを基に、ハマス戦闘員による虐殺や性的暴行、身体切断などの残虐行為を318ページにわたって詳述している。
これらの行為について「1200人近い罪のない人々が実際にハマスとその協力者によって殺害され、その多くは1937年の南京大虐殺以来、世界史上見られなかった残忍な蛮行の現場で殺された」と説明している。
昭和12年(1937年)の日本軍による南京攻略を巡っては、戦闘による死者が数万単位あっても、民間人に対する組織的虐殺はなかったことを示す説が多数発表されている。
一方で外務省はホームページで「日本政府としては、日本軍の南京入城後、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。しかしながら、被害者の具体的な人数については諸説あり、政府としてどれが正しい数かを認定することは困難であると考えています」と掲載し、英文でも発信している。
外務省のウェブサイトの記載は改変すべきであり、これは国会で取り上げていきたいと思います。
その際に重要なのが、根拠です。
1937年の南京攻略の際の重要人物を二人挙げます。
・松井石根(いわね)陸軍大将
・朝香宮鳩彦王(あさかのみややすひこおう)
松井石根氏は日中友好の意向を持っていたことが各種資料からは明らかです。
陥落した南京に入城する陸軍中将 朝香宮鳩彦王 上海派遣軍司令官。中島今朝吾第16師団長や南京一番乗りをした脇坂次郎歩兵第36連隊長の上官だった。 pic.twitter.com/8MwvdpFgII
— 領議門番(Gatekeeper of Yeongui) (@Ninigi_Yata) December 13, 2024
朝香宮鳩彦王の当時の行動が良くわからないので、今後の課題です。とは言え、当時の日本政府、日本軍によるいわゆる組織的関与の証拠を示すものがない以上、日本はこの南京事件に関する歴史戦を戦う必要はあるでしょう。
さて、松井石根陸軍大将による興亜観音へはいちどお参りに行きたいと思います。
論説委員・川瀬弘至 興亜観音の慈愛を世界にhttps://t.co/kKWhaRfYBX
日中戦争で上海派遣軍司令官を務め、南京攻略戦を指揮した松井石根陸軍大将が、私財を投じて昭和15年に建立した。理念は「怨親平等」。日中両軍・両国民の戦死者を、敵も味方も分けへだてなく慰霊するためだった。
— 産経ニュース (@Sankei_news) December 24, 2023
凜々(りり)しくも、穏やかな笑みをたたえていた。怒りも憎しみもなく、一切の苦痛から解き放たれたお顔だった。
静岡県熱海市伊豆山の中腹に建つ、高さ1丈(約3メートル)の「興亜観音」―。日本と中国の土を練り合わせて作られた赤銅色の観音像である。
その眼は遥(はる)か、中国大陸を見つめているという。
七士の遺骨
興亜観音は昭和12年に勃発した日中戦争で上海派遣軍司令官を務め、南京攻略戦を指揮した松井石根(いわね)陸軍大将が、私財を投じて15年に建立した。理念は「怨親(おんしん)平等」。日中両軍・両国民の戦死者を、敵も味方も分けへだてなく慰霊するためだった。
だが、その理念とは裏腹に、戦後は苦難の道をたどる。松井大将は戦争犯罪人として極東国際軍事裁判(東京裁判)にかけられ、「南京大虐殺」の冤罪(えんざい)で処刑された。
ちょうど75年前の冬、23年12月23日である。
このとき処刑された「戦犯」は松井大将、東条英機元首相、広田弘毅元首相ら7人。彼らがのちに神格化されることを恐れた占領軍は遺体を火葬し、遺骨を太平洋に撒(ま)いた。
しかし、東京裁判の日本側弁護人と火葬場関係者らが遺骨の一部を盗み出し、伊豆山の興亜観音に運んだ。松井大将から観音像の守りを託されていた住職の伊丹忍礼師は、発覚すればただではすまないと知りながら遺骨を引きとり、境内に埋めて隠したという。
遺骨の存在が徐々に知られるようになるのは、日本の主権が回復した27年以降だ。34年には観音像の近くに「七士之碑」も建てられ、吉田茂元首相が碑文を揮毫(きごう)した。
苦難は続く。
40年代半ばに安保闘争などが激しくなると、興亜観音は保守反動の象徴とみなされ、破壊工作の標的にもされた。46年12月には過激派・東アジア反日武装戦線が七士之碑を爆破する事件が発生、観音像にも爆弾が仕掛けられた。だが、不思議なことに導火線の火が途中で消え、観音像は無事だった。
その後も悪質ないたずらや嫌がらせで、境内の備品などが壊される被害が相次ぎ、現在に至っている。
法灯を守れ
「つい最近も、入り口に取りつけていた『興亜観音』の看板が何者かに外され、参道に打ち捨てられていました」建立時から続く支援組織、「興亜観音奉賛会」理事の沢飯敦さん(52)が話す。
「ですが、そんな怒りも憎しみも『怨親平等』の慈愛で包み込んでしまうのが、この観音様なのです」
初代住職の伊丹師が昭和60年に死去した後、寺院としての興亜観音は妻の妙真尼と3人の娘たち(妙徳尼、妙珖尼、妙浄尼)が住職を受け継ぐなどし、法灯を守ってきた。
一般の宗教法人と異なり、墓地もなく檀家(だんか)もいないため、収入は奉賛会の会費などごくわずかである。
しかも今年、興亜観音はかつてない試練に直面する。7月に伊丹家最後の住職、妙浄尼が死去したのだ。12月には境内の維持管理などに長年尽くしてきた寺務職の男性(77)の自宅兼事務所が失火で全焼し、男性も負傷した。
奉賛会代表らが奔走したことにより、妙浄尼のあとは県内の別の寺院の住職に兼務してもらうことになった。一方、全焼した事務所の再建を含む境内の維持管理は寄付金などがなかなか集まらず、「大変厳しいのが実情です」と沢飯さんは表情を曇らせる。
だが、法灯を消すわけにはいかない。
怨親平等の理念
沢飯さんの案内で興亜観音を訪ねたのは12月中旬である。バス停から急坂を上ること10分余り、深い雑木林から浮かび上がるように立つ観音像の、慈愛のまなざしに息をのんだ。女性にも見え、男性にも見えるお顔は、戦死した青年将校のようにと、松井大将が製作者に依頼したからだという。
本堂までいくと急に視界が開け、相模湾が一望のもとに見渡せた。さざ波が冬陽(ふゆび)を浴びて、きらきら輝いていた。
昨年にロシアがウクライナに侵略し、今年はガザで悲惨な戦闘が始まった。世界はいま、怒りと憎しみに満ちている。
怨親平等のまなざしが、この海の向こうにも注がれることを、願ってやまない。(かわせ ひろゆき)
興亜観音については、税金を使ってでも維持してほしいと思います。